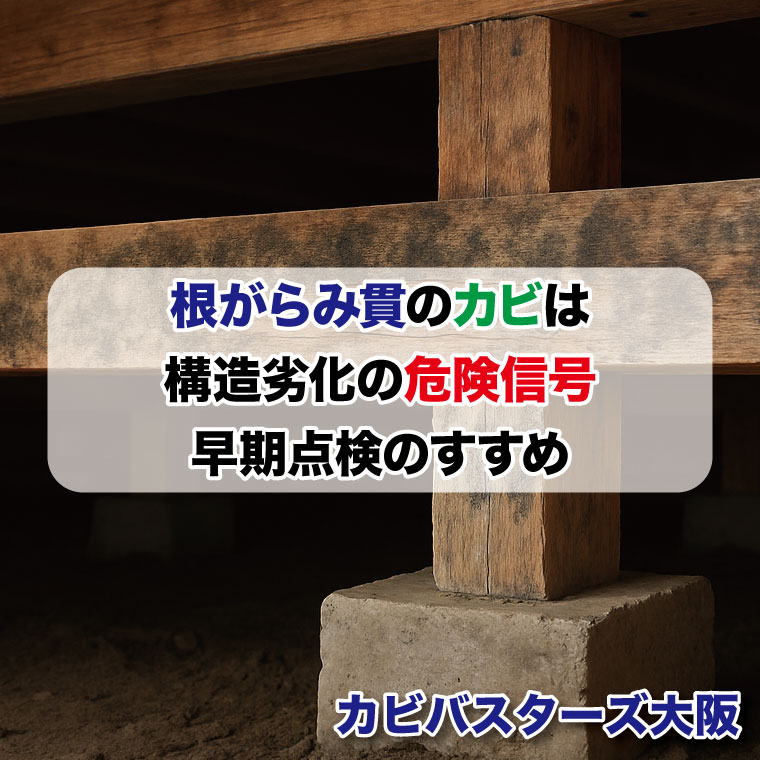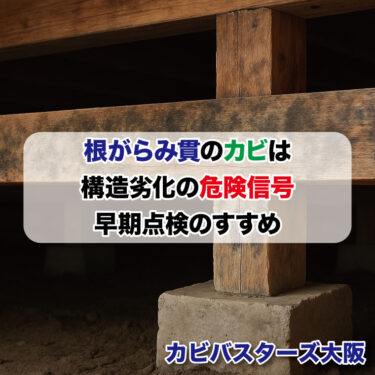木造住宅の床下に使われる構造材「根がらみ貫」がカビの温床になっているケースが増えています。見た目ではほとんど気づかない場所で起きるカビは、気づかないうちに木材を腐朽させ、耐久性や安全性を脅かす可能性があります。
本記事では、根がらみ貫の構造的役割やカビ発生の原因、正しい確認方法と具体的なカビ対策、そして専門業者による対応までを詳しく解説します。
住まいの健康と快適性を守るため、床下構造の見落としがちなポイントもしっかり理解できるようご案内します。
1. 根がらみ貫とは?構造上の役割とカビの問題
住宅の床下に使われる「根がらみ貫(ねがらみぬき)」は、普段目にすることのない部材ですが、建物全体の安定性を支える重要な構造材のひとつです。その根がらみ貫にカビが発生してしまうと、気づかないうちに木材が腐朽し、床のたわみや沈み込みといった深刻な被害につながるおそれがあります。まずはこの部材の基本的な役割と、なぜカビの温床になりやすいのかを理解することが、正しい対策の第一歩です。
1-1. 根がらみ貫の役割/基本構造とは
根がらみ貫とは、建物の基礎に設置される床組の一部で、主に「束柱(つかばしら)」同士を水平につなぎ、全体のねじれや変形を防ぐ役割を持つ木材です。床下で水平に組まれているため、上からはまったく見えませんが、この部材があることで、床全体の荷重が均等に分散され、地震や経年劣化による歪みを抑制しています。特に地盤が不安定な土地や、重量物を支える床では、根がらみ貫の健全性が建物の耐久性に直結します。
1-2. 床下構造におけるカビの発生部位としての根がらみ貫
根がらみ貫が床下に設置されていることから、常に地面からの湿気や外気との温度差の影響を受けやすい環境にあります。さらに、床下は日光が差し込まず風通しも悪いため、湿度が高くなりやすい場所です。こうした条件が揃うことで、根がらみ貫にはカビが発生しやすく、しかも気づきにくいという厄介な特徴があります。
一度カビが発生すると、表面だけでなく木材内部にも根を張るように広がり、見た目以上に深刻なダメージを与えます。特に、古い住宅や防湿処理がされていない床下では、根がらみ貫のカビ被害が進行していても気づかれないまま放置され、後になって大規模な補修が必要になるケースも少なくありません。
2. 根がらみ貫にカビが発生する原因と背景
根がらみ貫は床下に位置するため、常に湿気の影響を受けやすい環境にさらされています。カビが発生する背景には、住宅の構造的な特徴や気候条件、建材の性質など、さまざまな要因が関係しています。ここでは、根がらみ貫にカビが発生しやすい根本的な理由と、その背景について詳しく見ていきましょう。
2-1. 通気不良・湿気・床下環境の問題
根がらみ貫にカビが発生する最大の要因は、床下の通気不良と湿気です。床下は地面に近いため、気温や湿度の変化を直接受けやすく、特に梅雨時期や台風の多い季節には、地面からの湿気が床下全体にこもりがちになります。加えて、床下の換気口が塞がれていたり、床下の構造が密閉されている住宅では、空気が流れず湿度が常に高い状態になり、カビの繁殖に最適な環境が作られてしまいます。
また、住宅周辺の水はけが悪い場合や、雨水が建物の基礎に溜まりやすい設計になっていると、床下の湿気がより深刻になります。このような状態が続くと、根がらみ貫だけでなく、床束や根太など他の構造材にもカビや腐朽が広がるリスクがあります。
2-2. 根がらみ貫材の材質や設置方法の特性
多くの根がらみ貫は、無垢の木材や集成材で作られており、これらは湿気を吸収しやすい性質を持っています。特に、木材表面に塗装や防湿処理がされていない場合、空気中の水分や床下の湿気を吸収しやすく、カビの胞子が定着しやすい環境になります。
さらに、根がらみ貫は床下の束柱を連結するように設置されているため、束石や地面に近い位置にあることが多く、地中からの水分の影響を最も受けやすい部材の一つです。このような位置関係も、根がらみ貫がカビの発生源になりやすい理由のひとつです。
3. 放置による影響:構造へのリスクと健康被害
根がらみ貫に発生したカビを放置してしまうと、時間の経過とともに被害は建物全体へと広がっていきます。床下のカビは静かに、しかし確実に木材を蝕み、住まいの安全性や住環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、構造面でのリスクと、住まう人の健康への悪影響について詳しく見ていきます。
3-1. 木材の腐朽と床組全体の耐力低下への影響
根がらみ貫がカビに侵されると、次第に木材内部にまで菌が入り込み、「腐朽菌」による分解が始まります。これが進行すると、木材は強度を失い、もろくなっていきます。根がらみ貫は床下の束柱を連結し、床全体のねじれや横揺れを抑える重要な部材です。この部分が腐朽すれば、床の水平バランスが崩れ、沈み込みや歪み、最悪の場合は床の破損につながる恐れもあります。
また、根がらみ貫の劣化は他の構造材にも連鎖的に影響を与えます。束柱や大引、根太など、床組の主要部分がバランスを欠くことで、住宅全体の耐震性や耐久性にも影響が及びかねません。初期の段階では目に見える変化が少ないため、気づいたときには大規模な補修が必要になるケースも珍しくありません。
3-2. カビから派生する健康リスクと住環境悪化
構造への影響だけでなく、カビは住まう人の健康にも大きな悪影響を及ぼします。カビが放つ胞子やカビ毒は、空気中に浮遊して室内に広がり、吸い込むことでさまざまな症状を引き起こします。特に小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方にとっては、喘息や咳、鼻水、皮膚トラブルなどの原因になることがあります。
さらに、床下からのカビ臭が居室にまで上がってくると、空気の質そのものが悪化し、快適な住環境が損なわれてしまいます。知らない間に住環境が悪くなり、家族の健康リスクが高まっているということもあり得るのです。
4. 根がらみ貫のカビを確認するチェック方法
根がらみ貫は床下の構造材であるため、日常生活の中でその状態を直接目にする機会はほとんどありません。しかし、カビが発生しているかどうかを早期に確認できれば、被害を最小限に抑えることが可能です。ここでは、専門知識がなくても実践できるチェック方法をご紹介します。
4-1. 点検口からの目視とカビの特徴チェック
多くの住宅には、床下点検口が設けられています。点検口を開け、懐中電灯などで床下を照らしてみると、根がらみ貫や周囲の木材の状態をある程度目視で確認することができます。特に注意すべきサインは以下のとおりです。
-
木材表面に白・黒・緑などの斑点が見られる
-
木材にふわっとした綿状の物質が付着している
-
カビ臭や湿っぽいニオイがする
これらの症状が見られる場合は、すでにカビが発生している可能性が高いため、放置せずに速やかに対処することが求められます。
また、点検口の周囲が異常に湿っていたり、結露が見られる場合も、床下の湿度が高くカビが発生しやすい環境であるといえます。見える範囲だけでも、定期的にチェックする習慣を持つことが重要です。
4-2. DIY点検で使える湿度計・照明・カメラ活用術
床下環境をより正確に把握するためには、簡単な道具を活用するのもおすすめです。たとえば「湿度計」を床下に設置しておけば、日常的に湿度の傾向を確認できます。湿度が70%を超える状態が続く場合は、カビが発生しやすい環境と判断できるため、対策の目安になります。
また、点検口から内部をのぞく際は、手持ちのLEDライトや小型の懐中電灯を使用すると、奥までしっかり確認できます。スマートフォンのカメラを使って写真を撮ることで、変化の記録や異常の発見にも役立ちます。最近では、小型の内視鏡カメラを点検用に使用する方も増えており、手軽に奥まった場所までチェックできるツールとして人気があります。
ただし、床下に自ら入り込むのは危険が伴います。天井が低く、動きづらい環境での作業は、体を傷めたり、建材を傷つけてしまうリスクがあるため、あくまで「見える範囲でのチェック」にとどめることをおすすめします。
5. 効果的なカビ対策:根がらみ貫へのアプローチ
根がらみ貫にカビが発生していた場合、表面だけを掃除するだけでは根本的な解決にはなりません。カビは木材の内部深くに根を張っており、適切な処理を行わない限り再発する可能性が高いのです。ここでは、根がらみ貫に対して実践できる具体的かつ効果的なカビ対策を紹介します。
5-1. 床下の換気・湿気管理と防湿処理
まず第一に取り組むべきは、床下全体の湿気対策です。カビの根本的な原因は湿気にあるため、床下の通気性を確保することが基本となります。たとえば、基礎に設置された換気口が塞がれていないか確認し、周囲の物を取り除いて空気の流れを妨げないようにします。
さらに、床下用の送風機(換気ファン)を設置することで、空気の滞留を防ぎ、カビが好む湿った環境を改善できます。地面がむき出しの床下には防湿シートを敷き、地面からの湿気の上昇を遮断することも非常に有効です。これにより、床下の湿度を安定させ、根がらみ貫へのカビ再発を防ぐ環境を整えることができます。
5-2. 専用薬剤による除カビ・防カビ処理の流れ
カビがすでに発生している根がらみ貫には、木材に対応した専用除カビ剤を使用して処理する必要があります。この除カビ剤は、表面に現れたカビだけでなく、木材内部にまで浸透し、根を断ち切るように作用するタイプが効果的です。
除去後には、防カビ効果のある薬剤を塗布し、再発防止の処理を施します。特に、MIST工法®のような特殊技術を使用すれば、木材を傷めずにカビの除去と同時に予防が可能であり、床下というデリケートな環境においても安全かつ確実な対策ができます。
また、防カビ処理は床下全体に広がっているカビ胞子にも作用するため、空気中の拡散を抑え、根がらみ貫以外の部材にも好影響を与えます。施工後はカビ臭も軽減され、室内の空気環境も改善されるというメリットがあります。
6. 根がらみ貫のカビ対策は専門家へ相談すべき理由
根がらみ貫に発生したカビは、表面だけをきれいにしても再発しやすく、床下という閉ざされた環境では再び湿気がこもり、短期間で同じ問題を繰り返すことが少なくありません。だからこそ、確実で安全なカビ対策を行うには、経験豊富な専門業者に相談することが最も確実な方法です。
6-1. プロの診断とカビ対策技術の優位性
専門業者は、単にカビを除去するだけでなく、「なぜその場所にカビが発生したのか」「どこまで被害が広がっているのか」を現地で詳細に診断することができます。根がらみ貫だけでなく、床板や大引、束柱など他の部材にカビが波及していないかを確認し、適切な対応範囲を判断します。
また、プロが使用する薬剤は市販品とは異なり、深くまで浸透し、木材内部のカビ菌まで死滅させる力を持つ専用剤です。これに加え、防カビ剤の施工もあわせて行うことで、再発を長期間にわたり防止できます。安全性にも配慮された成分を使用しているため、施工後も安心して生活できる環境が整います。
加えて、床下の構造や換気環境に応じた改善提案や、防湿処理・断熱施工などのオプション提案まで行えるため、原因の根本解決が可能なのも専門業者ならではの強みです。
6-2. カビバスターズ大阪が提供する、根がらみ貫向けサービスの特徴
「カビバスターズ大阪」では、木材や構造材に特化した除カビ技術を用い、根がらみ貫を含む床下構造部材の除カビ・防カビ処理を専門的に実施しています。最大の特徴は、独自開発のMIST工法®によって、木材を傷つけることなく深部のカビまでしっかり除去できる点にあります。
この工法は、素材にあわせた薬剤の濃度を都度調整し、湿気や素材の状態を丁寧に見極めながら処理を行うため、繊細な床下構造でも高い効果を発揮します。また、施工後は空気中に残るカビ胞子への対処や、防カビ処理による予防対策までワンストップで対応できるため、再発リスクを限りなくゼロに近づけることが可能です。
根がらみ貫のカビ対策は、カビバスターズ大阪にお任せください
床下の根がらみ貫にカビが発生してしまうと、建物の耐久性や安全性を脅かすだけでなく、家族の健康をも左右する深刻な問題に発展する可能性があります。表面上の除去だけでは再発のリスクが高く、根本的な解決には専門的な知識と技術が必要です。
そこでおすすめしたいのが、カビバスターズ大阪です。私たちは独自開発のMIST工法®を用いて、根がらみ貫をはじめとする床下構造材のカビを素材を傷めることなく、深部まで徹底的に除去します。この工法は、こすったり削ったりする必要がないため、木材の劣化を防ぎながら、カビの根までしっかり処理できるのが特長です。
使用する除カビ剤や防カビ剤は、工業排水試験や各種安全性検査に合格した人体に優しい薬剤を採用しており、小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
さらに、除カビ後の防カビ処理によって再発防止までしっかりサポート。空気中に浮遊するカビ胞子への対応や、湿度の高い大阪地域特有の床下環境にも適したアプローチが可能です。
「床下に入って確認できない」「構造材の劣化が心配」「一度しっかり調べてみたい」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度カビバスターズ大阪にご相談ください。
あなたの大切な住まいとご家族の健康を守るために、私たちが全力でサポートいたします。