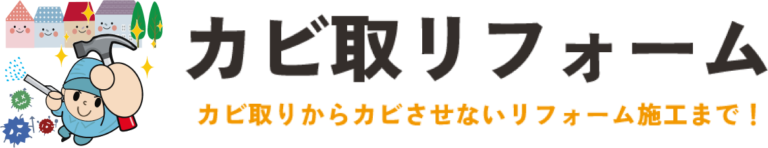問題提起
病院や医療施設で、天井や壁に見えないカビが繁殖していることをご存じでしょうか?特に壁・天井の含水率が高く、結露や通気不良が続く環境では、カビの胞子が室内に拡散し、患者やスタッフの健康に悪影響を与えるリスクが高まります。
記事を読んで分かること
本記事を読めば、なぜ医療施設でカビが発生しやすいのか、そのカビが人体にどう影響するか、施設運営に潜むリスク、そして具体的な除去・予防方法と再発防止のための体系的な対策法が理解できます。
記事を読むメリット
この情報をもとに、医療施設でも安全で快適な環境づくりが可能になります。アレルギー悪化や過敏性肺炎の予防につながり、施設の信頼性を保ちつつ、患者・スタッフ双方の安心を獲得できます。
医療施設、特に病院やクリニックなどでは、清潔性が最重要視される環境であるにも関わらず、天井・壁のカビ発生は意外と起こりやすい問題です。これは、構造・設備・運用が複合的に絡み合って湿気や通気の悪さを生み、カビ繁殖の条件が揃ってしまうためです。ここでは、なぜ医療施設でカビが発生しやすいのか、そのメカニズムと背景を詳しく解説します。 建材が持つ含水率とは、乾燥状態時に比べてどれくらい水分を含んでいるかを示す指標で、たとえば石膏ボード、木材、断熱材、塗料層などにはある程度の水分が内部に存在します。通常、これらの含水率は限られた範囲内で推移しますが、環境が湿潤になったり水分供給が続いたりすると、その内部含水率が上昇します。 加えて、洗浄や清掃時の水の飛散、配管漏水、給排水設備の滴下、天井からの水漏れなどがあると、建材が部分的に水分を帯び、乾燥が追いつかないまま湿気を蓄えることがあります。こうして含水率が高まり続けると、表面に見えるカビ発生が起こる前の段階で、内部で菌糸が拡がっていることも珍しくありません。 建物設計および運用面での通気性・換気性の悪さも、カビ発生リスクを高める要因です。医療施設では感染対策や空調制御の都合上、気密性を高める設計が採られることが多く、これが裏目に出て湿気の逃げ場を失うケースがあります。特に以下のような状況が発生しやすくなります: 通風が滞るデッドスペース:天井裏や壁裏、配線・配管経路、梁下空間などに空気の流通がない空隙が存在すると、湿気が滞留しやすくなります。 換気回数不足:空調設備の換気モードや外気導入量が設計上の計画通り動作していないと、室内湿度が高止まりします。特に湿度の高い季節や多湿地域では、換気を絞って冷暖房効率を優先した運転がなされることがあり、これが逆に湿気蓄積を助長します。 設備配置による遮蔽:医療機器、配管架設、空調ダクト、ケーブルラックなどの配置によって、天井・壁間の空気流通が妨げられることがあります。これにより、湿気が滞留する場所ができてしまいます。また、エアコンの冷媒管や空調ダクトの近傍では温度差が激しくなるため結露が発生しやすく、カビリスクが高まります。 さらに、エアコンや換気装置自体がカビの発生源となることがあります。冷房運転時には空調内部に結露水が発生しますが、この水がドレン配管の詰まりなどで適切に排水できなければ、冷却器盤やドレンパンに水分が残留し、そこにカビが繁殖する可能性があります。これが空気経路を通じて室内各所に胞子をまき散らす原因となります。 このように、「含水率上昇」と「通気・換気不良」が組み合わさることで、医療施設の天井・壁はカビ発生にとって非常に脆弱な環境になってしまうのです。 医療施設内で天井や壁にカビが発生していると、たとえ目には見えなくても、空気中の胞子や代謝産物を通じて人体や施設全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、天井・壁カビが引き起こす“見えないリスク”を丁寧に解説します。 カビの最大の脅威は、「空気中に浮遊する胞子」です。これらは微小な粒子であり、人間の呼吸器を通じて容易に体内に取り込まれる可能性があります。カビ胞子の拡散経路には、以下のようなものがあります: 天井裏→エアコン吹出口:天井裏や隠蔽空間で繁殖したカビの胞子がダクト経由で室内に送り込まれることがあります。エアコンの吹出口や換気口を通じて、吹き出し風と共に室内に拡散します。 壁内→配管孔・電線孔:壁の中で繁殖した菌糸体や胞子が、配管スリーブ・電線孔などの隙間を通じて室内に進出します。特に築年数の古い建物では、こうした隙間が多く、外部との気圧差で微少気流が生じ、胞子が押し出されるケースもあります。 目に見えない表面付着:壁紙の下層、塗装層の微細なひび割れ、クロス接合部など、表面から見えない微小な凹凸部分でカビが付着し、乾燥した空気の流れによって胞子が剥がれ落ちてくることがあります。 エアコン内部・フィルター溜まり:空調ユニットの内部、吸込グリル、フィルター裏側、ダクト内壁などにカビが成立すると、運転時にその胞子がエアフローに乗って施設内に拡散します。 これらの拡散経路は目に見えにくいため、施設管理者が直接気づくことは難しく、被害が進行した後に発見されることが多いです。 カビそのものの胞子だけが問題なのではありません。多くのカビは代謝活動を行い、その過程で「マイコトキシン(真菌毒素)」と呼ばれる物質を生産します。これらはごく微量でも有害で、慢性的な曝露によって健康に影響を及ぼす可能性があります。 マイコトキシンの性質:発がん性、肝障害、免疫抑制、神経毒性などを持つ種類が報告されています。一部は空気中にも揮発性または気相移行しやすく、吸入され得ます。神経系・肝機能・免疫系に影響を与える可能性があります。実際に医療施設でマイコトキシン濃度が局所的に上昇したとの報告もあります。 慢性曝露リスク:短期的な高濃度曝露ほど明確な症状は出にくいものの、長期間低濃度に曝露され続けることがアレルギー症状の増悪、疲労感、頭痛、集中力低下などの原因となるケースも報告されています。特に免疫力が低下している患者にとっては、毒性の影響が顕著になるリスクがあります。 二次代謝産物・揮発性有機化合物(MVOCs):一部のカビは揮発性の代謝産物を放出し、それが室内空気を“カビ臭”と感じさせたり、刺激性のあるガスとして呼吸器に作用を及ぼす可能性があります。これらもマイコトキシンと併せて、健康影響を複合的に引き起こすリスク因子になります。 医療施設という閉鎖性の高い空間では、これらの微量物質が濃縮されやすく、長期的な曝露リスクが高まります。症状としては、くしゃみ・鼻閉・咳・目のかゆみ・頭痛・倦怠感など非特異的なものから、慢性呼吸器症状や免疫機能低下など深刻なものまで現れる可能性があります。こうした見えないリスクを軽視することは、患者・スタッフ双方にとって重大な脅威です。 天井や壁に潜むカビから放出される胞子・代謝物は、吸入を通じて人体に侵入し、呼吸器系や免疫系に様々な影響をもたらします。特に医療施設においては、アレルギー体質者、呼吸器疾患患者、免疫抑制患者などが多く存在するため、影響は顕著になり得ます。この章では、カビが引き起こす具体的な健康影響を、以下の視点で整理して解説します。 カビ胞子は、いわばアレルゲンの一種として作用します。アレルギー感受性を持つ人がこれを吸入すると免疫系が過剰に反応し、以下のような症状が現れやすくなります: アレルギー性鼻炎:くしゃみ、鼻水、鼻づまり、鼻のかゆみなどが典型的な症状です。これが慢性化すると、副鼻腔炎などの併発リスクを高めます。 結膜炎・目のかゆみ:カビ胞子やその代謝物が目の粘膜に刺激を与えることがあります。 咳・喘息の誘発・悪化:特に気道過敏性を持つ患者では、カビ胞子が気道に入ると気管支平滑筋が収縮して喘息発作を誘発したり、既存の喘息症状を悪化させたりします。継続的な曝露が慢性化すると、喘息のコントロールが困難になるケースもあります。 医療施設においては、これらの症状を持つ入院患者あるいは通院患者が多く、カビ曝露が回復を阻害したり治療経過を乱したりする可能性があります。 カビは単なるアレルギー性反応だけでなく、過敏性肺炎(Hypersensitivity Pneumonitis, HP)や肺炎様症状を引き起こす可能性があります。過敏性肺炎とは、環境中微粒子(カビ・細菌産物・有機粉塵など)を吸入することで肺の間質に過剰な免疫反応が起き、肺炎類似の変化を引き起こす疾患群です。 過敏性肺炎の発症メカニズム:カビ胞子や代謝産物が肺胞壁や間質に沈着し、これに対する免疫応答が繰り返されることで間質性肺炎様の炎症を引き起こします。症状としては、発熱、呼吸困難、間質性肺炎像、肺機能低下、呼吸音の異常などが現れます。 慢性化および線維化のリスク:長期曝露が継続すると、肺組織が線維化を起こし、可逆性を失うことがあります。特に高齢者や既往に肺疾患を持つ患者では進展リスクが高まります。 免疫抑制患者との相互作用:がん治療中、ステロイド治療中、臓器移植後、膠原病治療中など免疫系が抑制されている患者は、通常は防御できるレベルの微量カビ曝露でも、感染性の真菌症を起こす可能性があります。アスペルギルス感染症、ニューモシスチス肺炎、クリプトコッカス症など、重症化リスクのある真菌感染を併発する場合があります。 医療施設内でのカビ曝露は、こうしたリスクを孕むため、特に免疫低下状態の患者にとっては重大な脅威となります。 医療施設では、患者の基礎疾患や免疫状態に応じて、カビ曝露のリスクや影響の出方が大きく変わります。ここでは、特に注意すべき患者層と、実際に報告されている症例を紹介しながら、どのような対応が求められるかを解説します。 以下のような患者層は、施設内カビ問題に対して特に脆弱です: 免疫抑制患者:がん化学療法、放射線治療、免疫抑制薬投与(ステロイド、抗TNF薬、抗リウマチ薬など)、臓器移植者など。彼らは通常の健康な人では防げる真菌侵入でも重篤な感染症を起こすリスクがあります。 術後患者・集中治療患者:手術創部や人工器具・カテーテルが挿入されている状況下では、局所感染を起こすリスクが高まりやすく、周辺環境の衛生性が極めて重要です。 高齢者・基礎呼吸器疾患患者:COPD、心肺機能低下、慢性肺疾患などを有する患者は、呼吸機能の低下からカビ誘発性の呼吸症状に対する耐性が低下しています。 小児・未成年児:気道が細く、呼吸器系の発達途上であり、カビ曝露による影響を受けやすい傾向があります。 これらの患者層においては、わずかなカビ曝露でもアレルギー反応、感染リスク、呼吸機能悪化を誘発しやすくなります。従って病院環境は、これら高リスク患者を基準にして高いレベルの衛生対策を設計すべきです。 実際の医療施設での報告事例をもとに、リスクがどのように現実化するかを把握しておくことは有用です。以下は報告事例の一部を整理したものです: 入院患者の過敏性肺炎発症例:ある病院で、カビ汚染が疑われる病室に長期入院していた患者数名に発熱・呼吸困難を伴う肺炎様症状が出現し、環境調査で天井裏の壁内にカビが繁殖していたことが判明。除去後に症状改善を認めた例があります。 免疫抑制患者の真菌感染:化学療法中の白血病患者が在院中に肺部アスペルギルス感染を発症し、環境調査でエアコンダクトや天井裏にアスペルギルス属菌の痕跡が見つかった例があります。抗真菌薬治療を行うも長期化、入院期間延長を余儀なくされたケースも報告されています。 高齢者施設併設病院での呼吸器悪化:高齢入院患者の中に、季節ごとに咳・喘息様症状の増悪を繰り返す例があり、施設改修時の壁内部調査でカビ繁殖が確認された例があります。除去処理後、呼吸器症状の頻度が低下したという報告もあります。 スタッフ健康被害と訴訟リスク:ある病院では、清掃スタッフが長期的に天井裏のメンテナンス作業を行った後、呼吸器アレルギー症状を訴え、環境調査で高濃度カビ胞子が検出された例もあり、労災・賠償問題に発展したケースがあります。 これら事例は決して珍しいものではなく、特に老朽施設や改変歴のある医療施設では発生リスクが高まります。したがって、医療機関は症例リスクを想定し、事前の環境モニタリングと予防策を講じておくべきです。 カビ問題は健康被害だけで終わらず、医療施設運営に対しても多面的なリスクをもたらします。ここでは、施設運営上の視点から、カビ被害がもたらすリスクと、それを回避するための戦略を示します。 医療施設は、患者やその家族の期待と信頼を背負っています。カビ被害が明らかになると、以下のようなリスクが発生し得ます: 患者クレーム・損害賠償請求:呼吸器症状やアレルギー悪化、長期入院を余儀なくされたケースで、施設が管理責任を問われ、賠償請求や訴訟に発展する可能性があります。 労働者安全責任追及:スタッフが長期曝露による健康被害を訴える場合、労災認定や安全配慮義務違反が問われることもあります。 評判低下・信用失墜:カビ問題が公表されると、口コミやメディアでの拡散リスクが高まり、施設の信頼性・ブランド価値が低下します。特に「清潔さ」「衛生管理」が重要視される医療機関では、評判の失墜が患者数減少につながることもあります。 行政監査・認定取り消しリスク:医療施設として満たすべき衛生基準に抵触したと判断されれば、保健所・医療行政から指導や改善命令を受けたり、認定外扱いとされる可能性もあります。 これらリスクは、カビ対応を怠ることで施設側に多大なコストと信用失墜をもたらします。 医療施設は、清掃衛生、建築衛生、空気環境基準など、さまざまな法令・ガイドラインに準拠する必要があります。カビがこれら基準に抵触する場合、以下のような影響が考えられます: 建築衛生法・病院設備基準:壁・天井の防湿・通気構造、換気回数、清掃の義務など、建築・環境衛生基準が定められています。これらを逸脱すると指導対象となります。 空気環境基準:医療施設では空気質(浮遊粒子、カビ菌数・濃度、温湿度管理など)が求められる場合があります。カビ胞子濃度が高い状態が常態化していると、基準逸脱として是正指導を受ける可能性があります。 感染対策指針:医療ガイドラインにおいて、院内環境管理や微生物抑制対策が求められており、これを守らないと医療安全上の問題となります。 保険償還・認定制度への影響:認定病院制度や施設格付け評価において、清潔性・衛生管理体制が評価対象となるケースがあります。カビ問題が露呈すると、評価減点や見直しを求められる可能性もあります。 運営上のリスクを軽視せず、法令・ガイドラインに照らした「予防可能な衛生戦略」を構築しておくことが不可欠です。 医療施設で発生したカビをただ放置するわけにはいきません。ここでは、現場担当者がまず取り組むべき除去・改善策を紹介します。これらは即効性こそ限定的でも、正しい運用と組み合わせることで被害の拡大を抑える礎となります。 カビ対策の基礎は、湿度・温度の制御と適切な換気に尽きます。以下が基本戦略です: 湿度コントロール:室内湿度は一般的に50〜60%程度を目安とし、これを超えないように管理します。湿度計を各所に設置し、リアルタイムで監視するとともに、除湿器、空調除湿運転の活用を行います。 温度管理:温度差を抑えることで結露リスクを減らせます。急激な冷暖房運転は避け、温度変動を緩やかにする運転方式(緩温運転)を選択します。 外気導入量確保:空調ユニットでの外気導入比率を確保し、室内空気を適切に更新することで湿気蓄積を防ぎます。ただし外気が高湿な場合、除湿処理が併用できるシステム設計が望まれます。 送風・循環空気制御:天井裏・壁間・床下空間の空気流通を確保するため、局所ファンや換気ダクトを設け、閉塞空間の換気を補助します。乾燥風を送ることが有効な場合もあります。 空調運転モードの最適化:除湿優先運転モード、夜間のデシカント除湿併用、運転の切替を工夫することで湿度抑制効果を高めます。 これらの運用改善により、カビ発育限界域から空間を遠ざけることが可能です。 運用のみで改善不十分な場合、構造・設備に手を入れる必要があります。以下が主要な改善策です: 防湿層/防水処理:壁裏・天井裏に防湿フィルムや透湿制御膜を設置し、外部・構造材からの湿気侵入を防ぎます。特に外壁面接近部については、防水・防湿層の強化が重要です。 断熱補強:壁層間の断熱材不十分な部分を補充し、結露を抑える温度差緩和性能を向上させます。断熱材選定には吸湿性の低い材料を選ぶことが望まれます。 配管・給排水設備の見直し:給排水管、空調冷媒管、ドレン設置のルート、配管支持部の防滴処理、ドレン管の傾斜・詰まり防止措置を講じ、漏水や滴下リスクを排除します。 壁材・仕上げ材の見直し:従来の石膏ボードやクロスよりも、耐湿・防カビ仕様の建材(防カビ処理されたボード、透湿性高材、抗菌性塗料等)を採用することで、カビリスクを低減できます。 気密調整:壁・天井の隙間や継ぎ目をシーリング処理することで、構造材内部への湿気浸入を防ぎ、空気経路を遮断します。 これら改善策は初期投資や工事が伴いますが、中長期的観点では被害拡大を防止し、維持コストを抑えるうえで極めて有効です。 現場改善で完全に対応しきれない場合、専門業者による除去技術や先進工法を導入することが鍵となります。ここでは、業者導入時のチェックポイントと技術導入事例・効果を紹介します。 専門業者を選ぶ際には、以下の観点を重視すべきです: 微生物科学的知見と技術能力 除去工法の選択肢と素材適応性 安全性・環境配慮 再発防止施策・保証制度 施工実績と信頼性 これら点を押さえた上で、信頼できる業者を選ぶことが、除去成功と再発抑制の鍵となります。 以下は、実際に導入された高度除去技術や工法と、その効果を示す事例です: MIST工法導入事例(医療施設) 紫外線照射+強制乾燥併用事例 HEPAフィルター併設空調システム改修事例 構造改修併用施工事例 これらの事例は、単純な除去だけでなく、再発防止までを見据えた総合的アプローチが成功の鍵であることを示しています。 除去後に再びカビが発生してしまっては意味がありません。持続的な安全環境を確保するには、再発防止策とモニタリング体制の構築が不可欠です。この章では、再発リスクを抑えるための戦略と、具体的なモニタリング手法を提供します。 除去後は、再発を早期に察知・抑止することが重要です。以下のような方法を体系化しておきます: 定期点検・目視調査:壁・天井・ダクト・設備裏面・隙間部など、重点リスクゾーンを月次・四半期単位で目視点検します。カビ嫌気臭、シミ・斑点の出現、湿気感など異常サインをチェックします。 空気中カビ菌数測定:定期的にサンプラーによる空気採取を行い、CFU(コロニー形成単位)換算で菌数を測定します。除去前後比較基準を設け、目標濃度を定めます。 壁面拭き取り試験:帯状テープ法、表面ぬぐい取り法(スワブ)を定期実施し、表面菌数をモニタリングします。これにより、隠れたカビの芽を早期検知できます。 温湿度データログ監視:室内・壁裏・天井裏など複数ポイントに温湿度センサーを設置し、リアルタイムでデータ収集。湿度が基準値を越えた場合のアラート設定と履歴保存を行います。 異常アラートと閾値設定:湿度上昇、菌数変動、温度変動、不快臭発生などをトリガーとしたアラート体制を構築します。 定期レポーティングとレビュー:月次や四半期ごとに環境報告書を作成し、関係部署・管理者に報告。改善点や傾向分析を行い、継続的改善プロセスとします。 このようなモニタリング体制を設けることで、再発兆候を早期に察知して対応できる仕組みが整います。 モニタリング体制を有効に機能させるには、担当者教育と実効性ある運用ルールが不可欠です。以下の要点を整備します: 担当者の定義と責任分担:施設管理部、清掃部、設備部、感染管理部門などが協働する体制を構築し、モニタリング・点検・対応の責任範囲を明確にします。 教育・研修プログラム:カビの基礎知識、見つけ方、緊急対応手順、清掃・除菌手法、モニタリング方法などについて、定期的に担当者研修を実施します。 早期警戒マニュアル:湿度上昇アラート、拭き取り異常値、異臭報告など発見時の初動対応手順をマニュアル化。速やかな部位隔離・調査・修復対応を規定します。 定期メンテナンススケジュール:空調フィルター清掃・交換、ドレン配管メンテナンス、隙間シーリング点検、換気設備点検などを定期計画で実行します。 改善フィードバックループ:モニタリング結果と実施対応を定期的にレビューし、制度改善・運用調整を継続的に行います。 長期記録保管と履歴分析:測定データ、点検記録、対応履歴を長期間保管し、年次傾向分析や年度比較ができるようにします。 このようなルールと教育体制を作り上げておくことで、一度取り除いたカビが再び勢いを取り戻すことを防ぎ、継続的に清潔な環境を維持することが可能になります。 医療施設・病院での天井や壁に発生するカビは、単なる見た目の問題ではなく、患者やスタッフの健康を脅かす深刻なリスクをはらんでいます。アレルギー悪化や過敏性肺炎などの健康被害、施設運営に対する信頼低下といったさまざまな問題に繋がる恐れがあるため、早期対応が求められます。 私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム名古屋/東京は、医療施設をはじめとする高い衛生基準が求められる建物において、専門技術である**MIST工法®**を駆使したカビ除去サービスを提供しています。MIST工法は、専用除カビ剤を霧状にして施工対象に均一に噴霧し、素材を傷めずにカビを根本から分解・除去します。薬剤は人体にも安全で、小さなお子さまや高齢者、免疫が低下した入院患者がいる環境でも安心してご依頼いただけます。 さらに当社では、株式会社タイコウ建装として建築リフォーム事業も展開しており、「カビ除去+リフォーム」を一括で対応可能な体制を整えております。たとえば、カビによって劣化した壁紙や下地材の張り替え、防湿・断熱改修、結露対策を施したリフォームを同時に行うことで、カビの再発を防ぎ、建物自体の耐久性と快適性を高めます。 「どこに相談すればよいかわからない」「カビだけでなく、設備の修繕や内装も一緒に頼みたい」といったお悩みに、私たちはワンストップで対応いたします。調査から見積り、施工、アフターフォローまで一貫して行うため、煩雑なやりとりや複数業者の手配に悩まされることもありません。 病院・クリニック・介護施設などの運営者様へ。1 医療施設でカビが発生しやすい理由
1.1 高含水率(壁・天井材の含水)と結露発生メカニズム
特に病院などの大規模建築では、壁・天井裏(天井スラブと仕上げ層の間、配管空間、空調ダクト空間など)において、湿気が入り込みやすい構造が多く見られます。外気との温度差が大きい季節には、内外の温度差で壁表面や裏面に結露が発生します。結露とは、空気中の水蒸気が冷たい面に触れて水滴になる現象であり、特に夜間冷える壁や天井裏、外壁に面した部屋で顕著です。こうした水滴や湿気が建材に浸透すると、含水率を高め、内部に湿った領域を作ります。これがカビにとって格好の繁殖場となります。1.2 通気不良・換気不足・設備配置の影響
2 天井・壁カビがもたらす見えないリスク
2.1 浮遊胞子・隠れたカビ拡散経路
2.2 マイコトキシンなど微量毒性物質とその作用
3 カビアレルギー・過敏性肺炎・呼吸器悪化:人体への影響
3.1 アレルギー性鼻炎・喘息悪化リスク
3.2 過敏性肺炎・肺炎様症状、免疫抑制との関係
4 医療現場で特に警戒すべき患者層と症状例
4.1 免疫抑制・術後患者、高齢者への影響
4.2 実際に報告されている症例・施設事例
5 カビ被害が施設運営に与えるリスク
5.1 訴訟・クレーム・評判低下の可能性
5.2 衛生基準・法令遵守の視点
6 除去および改善対策:現場でできること
6.1 湿度・温度管理・換気改善の基本戦略
6.2 防湿・断熱、配管漏水修繕、断熱材選定
7 専門業者導入・MIST工法など先進技術の活用
7.1 業者を選ぶ際のチェックポイント
- カビ菌種鑑定・胞子数測定・空気環境調査能力
- マイコトキシンの検出や揮発性代謝物質の測定対応
- 除去後残存菌数評価と除去証明対応
- 物理的除去(洗浄・拭き取り)
- 化学的除去(専用除カビ剤)
- 強制乾燥・熱処理・紫外線処理・オゾン処理併用能力
- 素材を傷めず安全性の高いものを選べる柔軟性
- 人体無害・環境無害な薬剤使用実績
- 揮発性有害性物質を残さない施工手順
- 防塵対策、清浄区域管理、養生対応能力
- 防カビコーティング、菌数バリア処理、再発抑制処理
- メンテナンス契約、定期点検、保証制度の有無
- 病院・医療施設での施工実績
- 施工事例・施主評価・公的施設実績
- 保証およびアフター対応体制7.2 成功事例・導入後の改善効果
MIST工法は、霧状の専用除カビ剤を微細に噴霧し、カビ胞子・菌糸に浸透分解させ除去する工法です。こすらずに素材を傷めず除去が可能なうえ、仕上げに防カビ剤処理を併用することで持続的な抑制効果を出す方法です。医療施設で導入した例では、施工前後の空気中カビ数が大幅に減少し、入院患者の呼吸器症状改善が報告されています。
医療法人向けの導入記事でも、MIST工法が素材に優しく、再発抑制効果が高い点が強調されています。
ある外科系病院では、天井裏に複数箇所でカビ繁殖が確認され、除カビ後に紫外線殺菌装置を設置し、強制乾燥空気循環を併用しました。これにより、施工後1年間で再発は認められず、患者の呼吸器症状の年間発生率が低下したと報告されています。
集中治療室や無菌病棟では、空調システムをHEPAフィルタ併設型に改修し、天井ダクトや送風経路を全面的に清掃・除菌。導入後、空中浮遊菌数低下とクレーム・訴訟対応件数の減少が報告された施設もあります。
築数十年の病院では、壁裏の防湿層劣化や断熱層不備を原因とするカビ発生が常態化していました。部分的な構造改修(防湿・断熱補強、壁材全面交換)とカビ除去を併用することで、再発頻度が大幅に低下し、通院患者の呼吸器症状の報告件数も減少したというデータがあります。8 再発防止とモニタリング体制の構築
8.1 定期点検・菌数測定・環境モニタリング方法
8.2 担当者教育・早期警戒体制・長期維持管理
カビ除去・リフォームはカビバスターズ大阪とカビ取リフォーム名古屋・東京へ
施設のカビ問題でお困りの際は、カビバスターズ大阪やカビ取リフォーム名古屋・東京にぜひご相談ください。プロの視点と高度な技術で、清潔で安心できる医療空間を再生いたします。